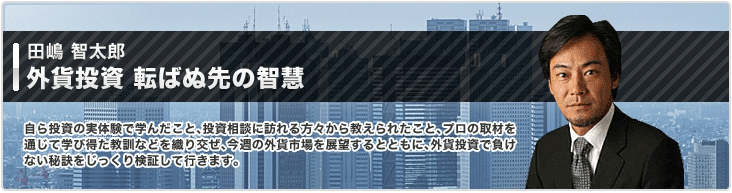先週17日、欧州中央銀行(ECB)は0.25%ポイントの利下げ実施を決定した。事前に利下げが確実視されていたことを考えれば、ここで一旦「材料出尽くし」ということになってもおかしくないのだが、理事会後のラガルド総裁の会見内容が市場に追加利下げへの期待をやや高めさせたことも事実である。
ラガルド氏は、今回の決定について「全会一致だった」と述べており、事前に「意見は分かれる」と見ていた市場にとってやや意外感があった。さらに、同氏は「経済成長のリスクは引き続き下振れ方向」、「消費や投資が想定ほど回復しない可能性がある」とも述べており、ECBが想定以上にハト派寄りであることを印象付けた。
結果、17日のユーロ/ドルは一時1.081ドル処まで値を下げたが、翌18日は一旦反発の動きを見せた。それは、一つに一目均衡表の週足「雲」下限が下値サポートとして機能したと見ることができると思われる。また、8月以降のユーロ/ドルは実にきれいな「ダブルトップ」を形成しており、そのネックライン水準から9月25日高値までの値幅をネックライン水準から下方に取った値=1.08ドル処が当面の下値の目途として意識されたということもありそうである。
ただし、18日に見られた反発の動きは「単に週末を控えたポジション調整目的のユーロ買いであった」と考えられる部分もないではない。
思えば、先週15日に発表された10月の独ZEW景況感指数や8月のユーロ圏鉱工業生産の結果は事前予想を上回るものであった。また、中国政府が打ち出している一連の景気刺激策がユーロ圏経済全体にプラスの効果をもたらす可能性もある。それにもかかわらず、今回のラガルド氏による数々の発言がかなりハト派寄りであったことは、やはり強いインパクトであったと言わざるを得まい。
先週のユーロ/ドルの週足ロウソクは、一目均衡表の週足「雲」の上方に終値で留まったが、当面は週足「雲」下抜けとなりやしないか要注目である。
一方で、ドル/円は依然として150円処に上値の壁があるように感じられる。足元で米10年債利回りが4%台を維持していることで、目先的にドルの下値は限られる格好となっているが、米債利回りが高止まりしている背景には米大統領選を控えて将来的な米財政悪化懸念が台頭していることも影響していると見ておかねばなるまい。
民主・共和両候補のいずれが勝利しても、米政府債務の一段の膨張は避けられないと見られることから、市場では今のうちに米国債を手放しておこうとする動きが見られており、結果的に“悪い金利上昇”が生じているといった側面もある。
先週17日に発表された9月の米小売売上高は予想以上に強い内容となったが、その背景にはガソリン価格の下落に加えて、小売り各社が価格競争を加速させた結果、大型セールや値下げが実施されたという実情もあった。
目下の米国では、労働所得の増加が頭打ちとなり、信用状況は悪化、家計は過剰貯蓄を使い果たし、今後は消費の伸びが鈍化する可能性も十分にあると見られる。
とまれ、目下のドル/円は依然として一目均衡表の週足「雲」上限の水準を上抜けられずにいる。150.80円処には7月高値から9月安値までの下げに対する半値戻しの節目があり、ほぼ同水準に一目均衡表の日足「雲」上限も位置している。むろん、上方に控える200日移動平均線は上値抵抗として意識されやすい。
米大統領選に相前後して一時的に151~152円あたりまで上値を伸ばす可能性もないではないが、仮にそうなった場合には日銀に与えられていたはずの『時間的猶予』がますます失われるという点も見逃せない。
(10/21 07:00)
FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-